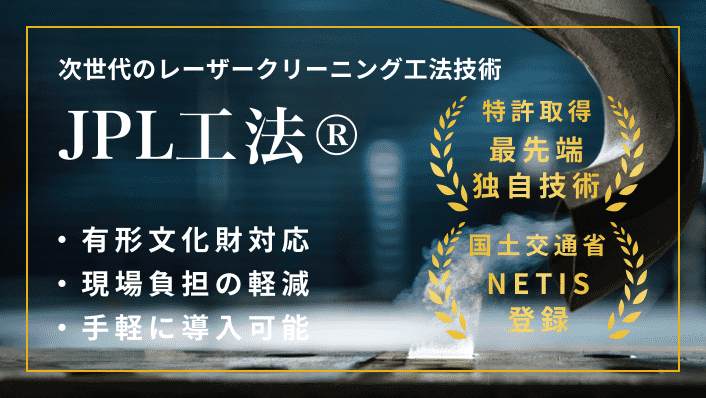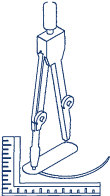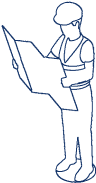共に作り つながり続ける。
助け合いが生む、現場の力
弊社では今、技術や人と人がつながっていくための下地を築いているところです。人も縁も、切ってしまえばそれでおしまい。つながり続けるのは努力が必要なこともありますが、その分必ず手元に返ってくると思っています。
人材不足解消のために外国人実習生を採用し始めて6年が経ちました。「あれ、こいつこんなにできたっけ?」半年前に入ってきた職員が知らない間に成長し、現場で活躍するのを見るのは嬉しいものです。彼らを日々指導している職人たちのおかげです。
外国人実習生は主にインドネシアやベトナムなど、アジアから採用しました。採用にあたって大切にしたこと―――それは、「状況を見て考え、自分で判断できる人物」かどうかです。
人を見て、助けられる者
周りを見て動ける者
そういった視点で採用を決めました。
例えば、一人が板をある場所に設置するため、持ち上げようとしている時。その板を設置するにはボルトが必要で、そんな時、誰かの指示を受けなくてもさっとボルトを差し出せる人。自然に他者を助けられる人物が、現場では非常に大切なのです。自分が主役であることよりも、二番手を張れる人、と言えるかもしれません。

若手が育ち、ベテランが輝く
採用した彼らは、とても純朴で素直な若者たちです。彼らを見て、逆に教えられることがありました。それは「言葉が通じず、技術もない。だからこそ、思いやりの循環が現場で生まれている」という事実です。
彼らを育成するのは古参の職人、それに対して外国人実習生は20代。親子ほどの年齢差があります。普段は口が悪く怖い職人たちですが、人情深い一面があるのです。言葉がわからない、仕事ができない、言ってもなかなかわからない。でも素直についてくる。そんな実習生を、「しょうがねえなあ」と面倒見よく関わっているのです。かわいがってやろうという親心が動くのでしょうか。
大切にしている道具を貸してあげたり、時には厳しく注意をしたり。実習生を同じチームの一員として見ているのでしょう、技術のない彼らを「気にかけなきゃ」という気持ちが職人に生まれているのだと思います。そしてそれを引き出しているのは、外国人実習生たちの素朴さです。ベテラン同士であれば、お互いに踏み込まないのが暗黙のルール。黙って自分の持ち場を訥々と進めるでしょう。必要以上の交流は生まれません。しかし、そこに言葉がわからない若者が加わることで、小さな交流が生まれるようになりました。良い現場作りに必要な良い人間関係ができつつあります。
同じようなことが、内勤のエンジニアとベテラン職員の間にも起こっています。20代後半のエンジニアたちは覚えが早く「なんでもやってみよう」の精神で70代のベテラン社員からどんどん技術を吸収しています。見積もり、積算、図面引きなど、今や彼らは、弊社にはなくてはならない戦力です。
そして驚くべきは、彼らが存在することによって70代の社員が若返っていることです。
一時期は技術の継承ができない中でモチベーションが下がる一方でしたが、今は同世代の人と比べても若く、元気でハツラツとしています。若手を育てなければという意識が「もうあと5年は頑張らなきゃ」という気持ちを引き出しているようです。自分の技術を吸収してくれる人がいるという事実は、「まだ自分は終わっていない」という情熱を心の奥に灯してくれるのかもしれません。
社長である私は、実習生やエンジニアの育成を現場の人間にまかせざるを得ませんでしたが、かえってそれが良かったのかもしれない、と今では思っています。

明日に希望を抱けるように
ある日、現場の実習生が、親方に道具を貸してもらったお礼に焼酎を買って返したい。どの焼酎を買えばいいか?と、先輩職人に訊ねてきた、という話を耳にしました。またエンジニアたちは、現場指揮をとる70代の先輩を乗せて、現場まで運転をしてきました。ふたりは現場での見積もりだけでなく、図面を起こし、製作に関わり取付け現場監督をして帰ってきます。今では先輩に代わり、工事のディレクションをこなせるようになりました。
例えるなら、大きな川では互いに関与しなかった者たちが、小川に入るとお互いを気にかける―――そんなイメージです。見てもらった人間も、してもらったことに対して恩を返す。小さな思いやりの循環が生まれています。
今年の春先に、私はエンジニアたちの出身地ベトナムを訪問しました。どんな時間を経て日本に来たのか、この目で見たかったからです。そこで彼らの暮らしを知り、多くの気づきを得ました。彼らが独り立ちできるくらいに成長した暁にも、彼らが望むなら我々とつながっていく術を手渡せるように。次のなにか、次のフェーズを常に用意できる企業でありたいと考えています。
子どもが巣立った後、一気に老けてしまう人を目にすることがあります。本質的な要因はどんどん歳を取っていくだけ――という絶望かもしれません。核家族化やその先の孤独死などの問題もありますが、事実上の命が尽きることだけが「死」ではないと私は思うのです。会社の中でも気持ちの上での孤独死が、あるのではないでしょうか。
気持ちが萎えてしまったり
気力が失せたり
何もトライできなくなった時、心が死んでしまいます。
未来を失うことがないように、明日に希望を抱けるように、企業として色々な事にトライしていかなければと考えています。
共にモノを作り、現場に納める。
彼らもまた、架け橋です。